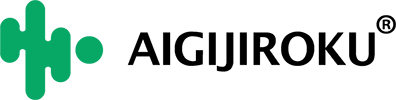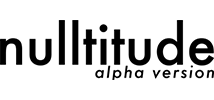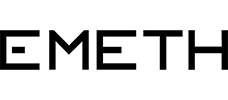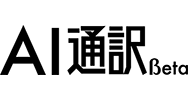近年、AI(人工知能)技術の進化は目覚ましく、そのなかでも注目を集めているのが「生成AI」と呼ばれる技術です。とくに2022年11月に「ChatGPT」が公開されてから、その勢いは加速度的に増し、各社・各業界での導入が急速に始まっています。
実際に、数多くの企業が生成AIを活用して業務改善や新規事業の立ち上げを進めています。たとえば、カスタマーサポートの現場ではチャットボットがリアルタイムで顧客の質問に対応し、商品説明や解決策を迅速に提示するケースも増えています。また、製造業の現場では設計プロセスで生成AIがアイデア出しを行うケースもあります。このような先進的な取り組みは、新しい技術への関心が高いスタートアップ企業のなかに留まらず、大手企業や地方の中小企業の間でも導入が進められています。
本記事では、生成AIの具体的な活用事例や導入に際しての課題について詳しく解説します。生成AIの持つポテンシャルをビジネスに活用したいと考えている経営者やご担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
生成AIとは

生成AIとは、与えられた入力データに基づいて新たなコンテンツを生成する技術を指します。この技術は、画像・テキスト・音声・動画など、多岐にわたる形式でコンテンツを生成できる点が特徴です。生成AIの代表的なモデルには、OpenAIのGPTシリーズや画像生成AIであるDALL-E、Microsoftが公開する音声生成AIのVALL-Eなどがあります。
従来までのAIが、主に既存のデータの分類や予測に特化していたのに対し、生成AIは新しいアイデアや表現を創出できる点が画期的だといわれています。この技術を活用することで、クリエイティブな作業の効率化や個別化されたユーザー体験の提供が可能になります。
そもそも生成AIの技術は、自然言語処理(NLP)や画像処理、深層学習の進化とともに発展してきました。そのため、人間に近い自然な言葉を生成したり、写真のようなリアルな画像を作り出したりする能力が飛躍的に向上しています。
昨今では、各業界で深刻な人手不足が叫ばれており、生成AIは人間が行う業務を代替できる技術として、大きな注目が集められています。実際に総務省の調査によれば、生成AIの活用による効果・影響について約75%が業務効率化や人員不足の解消につながると思う(「そう思う」と「どちらかというとそう思う」の合計)と回答しました。また、約65%がビジネスの拡大や新たな顧客獲得につながると感じているようです。一方で、情報漏洩や著作権侵害などのさまざまなリスクを感じている企業も一定数いることから、日本企業の生成AIの活用割合は、諸外国に比べて大きな遅れを取っているのも実情です。日本企業においては生成AIの活用はまだ発展フェーズであり、今後の成長に大きな期待が寄せられていることがわかります。
生成AIのビジネス活用事例

生成AIは、企業の業務効率化や新たなビジネス価値の創出に大きな貢献をしています。ここでは、日本国内で生成AIを積極的に活用する企業事例をご紹介します。
株式会社みずほ銀行
株式会社みずほ銀行は、国内全社員がテキスト生成AIを利用できる環境を構築しました。2023年6月には社内向け生成AI「Wiz Chat」を導入し、同年7〜8月にかけては生成AIに関するアイデアソンも行われ、社員2,000人以上の応募があるほどの盛り上がりを見せています。同行が次なるフェーズとして検討しているのが「事務手続照会」や「与信稟議作成」といった、多大な時間とリソースを要する業務の効率化です。現在、これらの業務で生成AIと社内情報を連携したチャットボットを構築し、試験的な導入を進めています。このプロジェクトでは、プロセスの効率化と正確性の向上が期待されており、銀行業務における生成AIの可能性を示す事例として注目を集めています。
参照:みずほFG:生成AI活用で、業務効率化と新たなイノベーションを実現(MIZUHO DX)
江崎グリコ株式会社
食品メーカーである江崎グリコ株式会社では、バックオフィス業務を効率化するため、AIチャットボットを導入しました。同社では、社内ポータルが点在していたことが原因で、従業員からの問い合わせ対応に時間がかかり、本来の業務が圧迫されていました。しかし、AIチャットボットを導入してからは、従業員が自分で解決できるようになり、従来まで13,000件/年あった問い合わせ件数が31%削減されました。チャットボットを案内するシールをPCに貼るなど、社内で浸透する工夫を施したところ「まずはチャットボットに聞いてみよう」という雰囲気が醸成され、各従業員の業務負担が軽減される結果となったようです。
参照:■導入事例■【Glicoグループ様】30%の社内問い合わせ対応を削減。顕在化したバックオフィスの課題を「Alli」で解決
株式会社日清製粉グループ
株式会社日清製粉グループでは、全社的に生成AIの活用を進めています。たとえば営業部門では、マクロトレンドや得意先の情報収集、プレゼン資料の骨子作成などの商談準備はもちろん、社内の進捗報告やMTGの議事録作成などの業務でも生成AIの活用を見込んでいます。これらの活用によって、1人当たり約400時間/年の工数削減を実現し、顧客のために使う時間を増加させることを目標に取り組まれているようです。また、営業部門での成功事例を他部署に横展開し、その過程で作成されたプロンプトテンプレートを全社的に展開していく予定でいます。同社では「AIを利用するかどうか」を個々の判断に委ねるのではなく、AIの利用を前提とした業務プロセスを確立していくことで、社内での浸透を図っているようです。
KDDI株式会社
KDDI株式会社は、社内版ChatGPT「KDDI AI-Chat」を開発し、グループ全体で約1万人の社員が自由に使えるようにしました。実際に社員の半数以上が活用しており、各社員が試行錯誤を重ねた結果、「かつては丸1日かけていたプログラミングの作業が2〜3時間で済むようになった」などの好事例も出てきています。同社では、AIの活用シーンを広げるために生成AIを使った業務効率化を競う「社内コンテスト」の実施や、社内大学での講義なども行っているようです。
参照:KDDIが実践する「生成AI活用」の現在地と未来 ビジネス展開を見据え、社内プロジェクトを推進|be CONNECTED.|法人のお客さま|KDDI株式会社
株式会社ビズリーチ
株式会社ビズリーチは、転職サイト「ビズリーチ」のなかで、転職希望者へのサポートとして生成AIを活用しています。具体的には、簡単な質問(職種、ポジション、業務のミッション、業務領域)に回答するだけで、職務経歴書の作成を自動で行えるサービスを提供し、利用者がより簡単に転職活動を始められるような取り組みを行っています。同社の調査によれば、AIで自動作成した職務経歴書と、使用していない職務経歴書で比較したところ、前者のほうが平均で40%多くのスカウトを受け取ることがわかったようです。
参照:ビズリーチ「GPTモデルのレジュメ自動作成機能」を開発 東京大学マーケットデザインセンターと共同で、GPTツールの性能評価を発表
株式会社伊藤園
株式会社伊藤園は、生成AIで作成した仮想タレントをテレビCMに起用しました。「お~いお茶 カテキン緑茶」を今から飲んでほしいという想いから、AIタレントが約30年後の未来の自分と現在の姿で出演することで、その魅力を伝えています。テレビCMのタレント起用に関しては、タレント自身の不祥事による差し替えや、出演料による広告宣伝費の高騰など、さまざまな悩みを抱えている企業が多いため、この取り組みは広告制作の新たな可能性を示す事例として注目を集めています。
参照:AIタレントを起用した「お~いお茶 カテキン緑茶」のTV-CM第二弾!新作TV-CM「食事の脂肪をスルー」篇を、4月4日(木)より放映開始 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト
株式会社ベネッセコーポレーション
株式会社ベネッセコーポレーションは「チャレンジ AI 学習コーチ」というサービスを提供しています。このサービスでは、学習中に生じた疑問をチャット形式でリアルタイムで解消することができます。疑問点があれば単語レベルで入力しても、AIがFAQの中から近いコンテンツを提供してくれるため、子どもでも安心して利用できる点がポイントです。また、AIが寄り添った会話で解決に導いてくれるため、学習効率を高める新しい教育モデルとして注目が集まっています。
参照:「進研ゼミ」が生成AI活用の新サービス「チャレンジ AI学習コーチ」を3月下旬から提供開始。教科の疑問を、いつでも納得いくまで質問可能に | 株式会社ベネッセホールディングスのプレスリリース
ウエインズトヨタ神奈川株式会社
ウエインズトヨタ神奈川は、Adobeの生成AI「Adobe Firefly」を活用することで、イベントのチラシ作成にかかる時間を従来までの1週間から、約20分にまで短縮することに成功しました。広告代理店やクリエイターとのコミュニケーション工数が削減されることで、マーケティング活動の迅速化とコストの削減などの効果が実現されています。
参照:ウエインズトヨタ神奈川がAdobeの生成AI導入、チラシ作成を1週間から20分に短縮 | 日経クロステック(xTECH)
生成AIのビジネス活用を進める際の手順

生成AIをビジネスの現場で取り入れる際には、下記のようなアプローチが求められます。
・活用目的/方針の整理
・利用システム/社内体制の構築
・試験運用
・実運用/改善
活用目的/方針の整理
まずは、生成AIを活用する目的や方針を整理することから始めましょう。たとえば「業務効率化」や「新しい製品・サービスの開発」など、いま企業で求められている分野での目標を設定し、それに基づいた具体的な実施方針を決めることが重要です。目的や方針が曖昧なままでは、その後の設計や運用のフェーズでつまづいてしまう恐れがあります。また、同様に的外れな設定をしてしまうと、生成AIを導入しても効果が得られないため注意が必要です。
利用システム/社内体制の構築
生成AIを活用する目的や方針が定まったら、つぎに利用するシステムや社内体制の構築を進めていきましょう。AIシステムの開発・導入を進めるIT部門のメンバーや、セキュリティ・プライバシーのリスクマネジメントを行う法務部門のメンバーなど、必要に応じてメンバーをアサインします。また、社員がスムーズに生成AIを活用できるように、研修やガイドラインの整備も必要です。
試験運用
利用するシステムや社内体制の構築ができたら、まずは小さな部門から試験運用を始めます。導入の初期段階では、思わぬトラブルが起きがちです。システムのエラーが起きたり、想定していたよりも利用が進まなかったりなど、実運用で心配になる部分も出てくるでしょう。しかし、試験運用だからこそ得られる気づきやフィードバックもあります。起こったトラブルを分析し、改善点を明確にして実運用に活かしていきましょう。
実運用/改善
試験運用を経たら実運用に移ります。運用を開始した後も、フィードバックを収集し、常に改善を図ることが重要です。AIに関するプロジェクトは導入がゴールになってしまう事例も少なくないでしょう。しかし、本来の目的は業務効率化や新規ビジネスの創出などにあるため、AIを導入して満足してはいけません。定量的なアンケートはもちろん、実際に使用している現場社員の声を直接聞き、さらなる活用を進めていく必要があります。
生成AIのビジネス活用を進める際の注意点

生成AIをビジネスの現場で導入する際には、下記のような注意点があります。
・法律に注意する
・社員のITリテラシー/倫理の向上に務める
・情報漏洩のリスク対策をする
法律に注意する
生成AIを使用する際には、著作権や肖像権などを侵害していないか注意が必要です。とくにキャッチコピーのライティングやクリエイティブの画像生成など、社外に公開する制作物については社内での確認が求められます。生成AIがアウトプットを行う過程で、インターネット上から収集したデータを読み込む場合にはとくに気をつける必要があります。社外への公開を想定される場合は、専門の弁護士や支援会社にご相談することをおすすめします。
社員のITリテラシー/倫理の向上に務める
生成AIを効果的に活用するためには、基本的なITリテラシーや倫理観の向上が不可欠です。そのためには、研修や教育プログラムなどを通じて、社員が正しくAIを活用できるようにすることが重要です。生成AIの使い方にとどまらず、その仕組みから理解を深めることで、各社員がビジネスへのさらなる活用を検討できるようになるでしょう。
情報漏洩のリスク対策をする
生成AIを利用する際には、情報漏洩のリスクについて徹底的な対策を行う必要があります。具体的には、顧客データや機密情報を入力しないようにする、仮に入力してもAIが学習データとして利用しないようにオプトアウトするなどが挙げられます。また、デバイスやシステムのセキュリティ対策も改めて強化し、リスクを最小限に抑える努力が求められます。
まとめ

生成AIは、人手不足が叫ばれる日本企業において業務効率化や新たなビジネス価値の創出をサポートする可能性を秘めています。実際に、先進的な取り組みを行うスタートアップにとどまらず、多くの大手企業や地方の中小企業の間でも導入が進められています。実際に導入を進める際には、まずは活用の目的や方針を整理し、試験運用を行ってから実運用に入りましょう。
生成AIの導入にはさまざまなメリットがありますが、一方でいくつかの注意点もあります。著作権や肖像権などの法律や情報漏洩などに注意したり、効果的な活用を図るために社員のITリテラシーを向上させたりなど、さまざまな整備が求められるでしょう。また、生成AIの導入を企画・開発するにあたっては高度なIT技術が求められます。とくに生成AIの分野は変化が激しく、最新のトレンドを社内でキャッチアップするのは時間がかかるため、専門の支援会社に一度相談をするのがおすすめです。
株式会社オルツでは、パーソナル人工知能を中心としたAI活用やDX推進を支援しています。課題のヒアリングからコンサルティング、実証実験まで一気通貫で行うほか、実際の開発や運用などの技術的な支援も可能です。少しでもご興味のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。